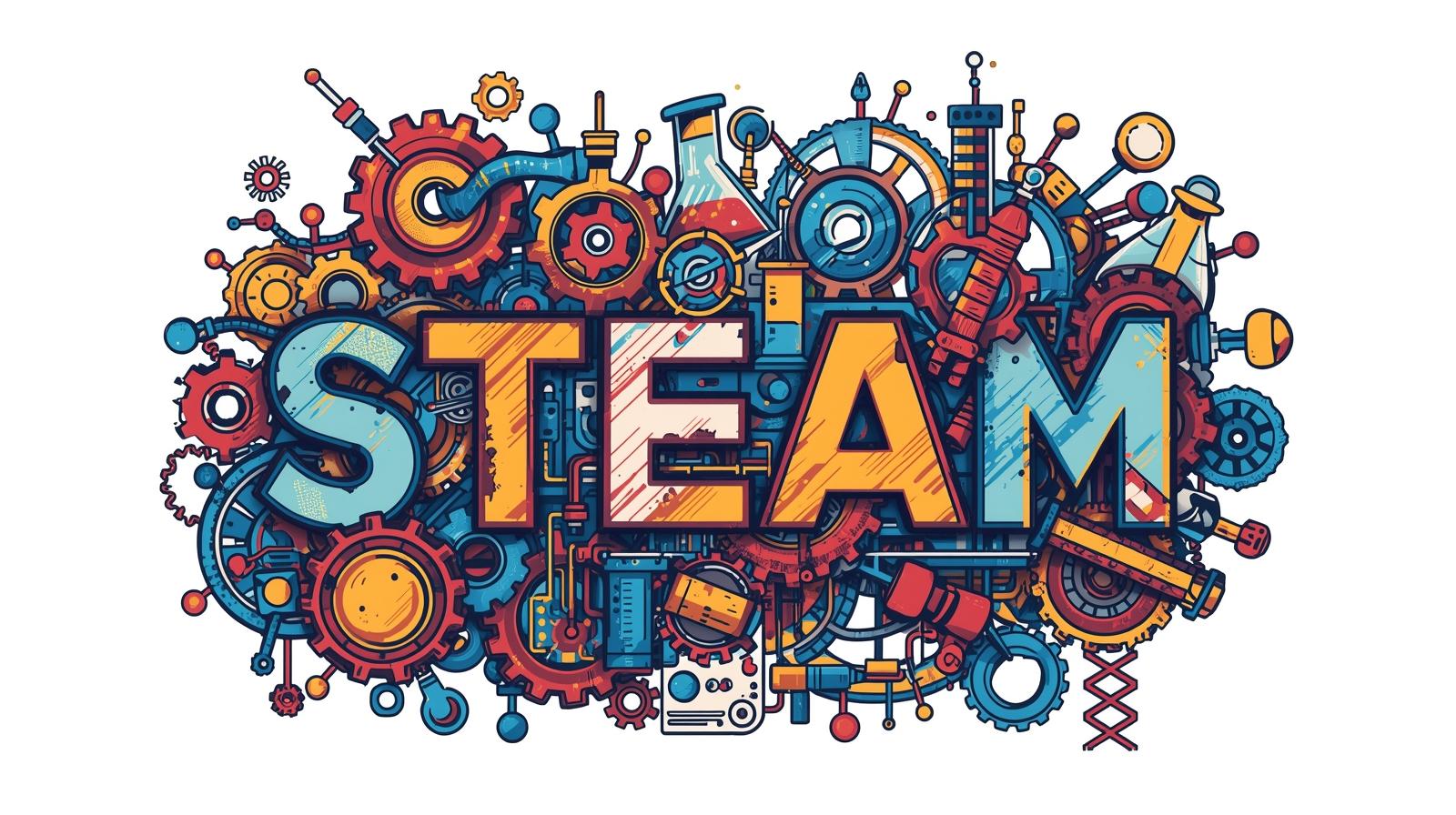学習塾、プログラミング、英語、プール…たくさん習い事があるけど、どれが本当にこの子のためになるんだろう?

『AIに仕事を奪われる』なんて聞くと、うちの子の将来がなんだか不安…
お子さんの習い事を考え始め、こんな風に悩んでいませんか?
私たちの社会は、AIなどの技術によって、ものすごいスピードで変化しています。これまでの「テストで良い点をとる」ことだけでは、この先の未来を力強く生き抜くのは難しい、と世界中の専門家が考えています。
そんな新しい時代に求められる力を育む教育法として、今、世界中から熱い視線を集めているのが「STEAM(スティーム)教育」です。
この記事では、「STEAM教育って一体なに?」という基本から、それを学んだお子様が「実際に、どんな大人になり、どう活躍しているのか」まで、具体的な事例を交えて分かりやすく解説していきます。
この記事を書いた人

- 技術士(機械部門)
- 社内教育や、国内大手メーカーの技術者教育、公的教育機関での講師経験多数
- 現在はヒューマンアカデミージュニアのロボット教室、こどもプログラミング教室、科学教室を運営
そもそもSTEAM教育ってなに?
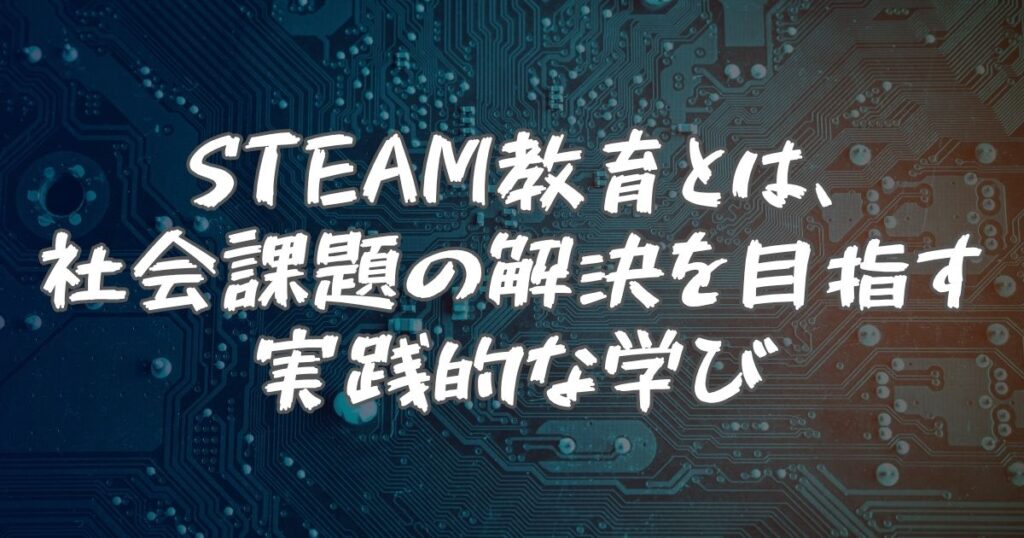
STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)という5つの分野の頭文字を組み合わせた言葉です。
でも、これは単に理科や算数をバラバラに学ぶのではありません。これらの知識を道具のように使いこなし、社会の中にあるリアルな課題や謎を解き明かしていく、実践的な学びがSTEAM教育の本質です。
一番のポイントは「A(アート)」
もともとは理数系の「STEM(ステム)教育」が始まりでした。しかし、技術の知識だけでは、人々の生活を本当に豊かにするような新しいものは生まれづらい、ということが分かってきたのです。
そこで加えられたのが「A(Arts)」。
これは、絵や音楽といった「芸術」だけでなく、文化や歴史、法律、そして人の気持ちを思いやる心といった、人間を深く理解するための幅広い教養(リベラルアーツ)全体を指します。
技術(STEM)に、人間を理解する心(A)が加わることで、初めて本当に世の中の役に立つものが生まれる、という考え方なのです。
文系・理系は関係ありません
「うちの子は理数系じゃないから…」と思った方もご安心ください。
STEAM教育は、むしろ日本の教育が長年抱えてきた「文系」と「理系」の壁を取り払おうとする試みです。文系・理系の枠を超えて、物事を多角的に見る力を育てます。
どんな「力」が身につくの?
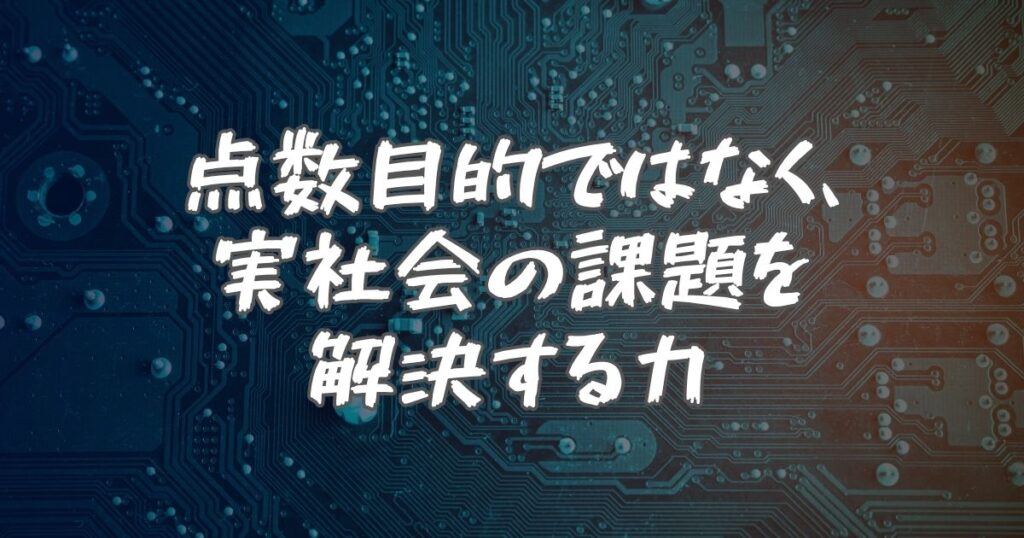
STEAM教育は、テストの点数がすぐに上がるような学習塾とは違います。もっと本質的な、これからの社会で不可欠となる「力」を育みます。
自分で課題を見つける力
これまでは、先生から課題を与えられて、すでにある正解を早く正確に求めればよかったです。しかし、STEAM教育では「商店街がさびしいな」「どうしてお年寄りは困っているんだろう?」といった、身の回りの課題を自分ごととして見つけることから始まります。
あきらめずに工夫する力
答えは一つではありません。実験やものづくりで失敗しても、それは学びのチャンスと捉えられます。何度も試行錯誤する中で、粘り強さや「まずやってみよう」という挑戦する強い心が育ちます。
みんなと協力する力
一人では解決できない難しい課題に、チームで取り組みます。自分と違う意見を尊重し、みんなで一つの目標に向かう中で、本物のチームワークが身につきます。
【事例紹介】STEAM教育を受けた子の、リアルな将来の姿
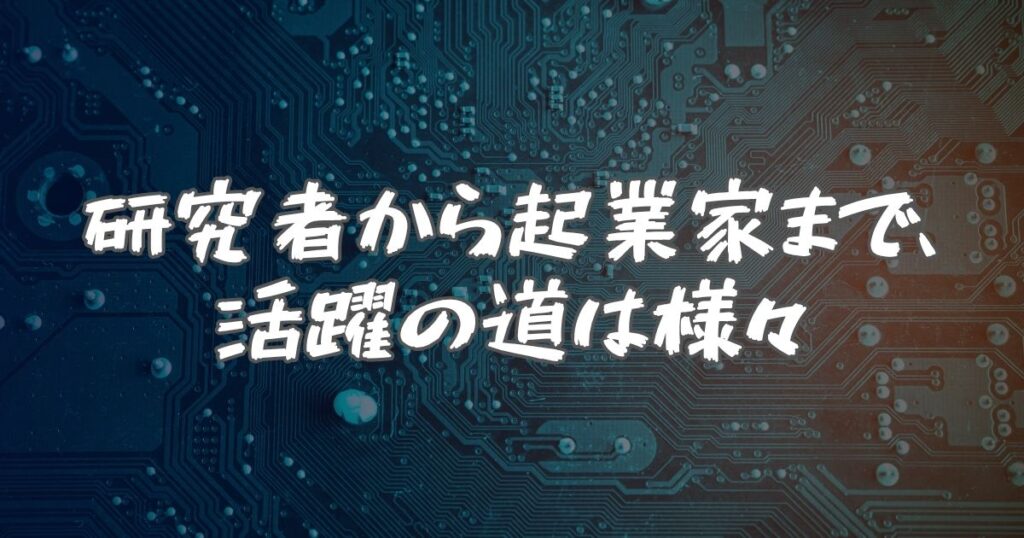
「で、結局、うちの子の将来にどう役立つの?」
その疑問に答えるため、実在する人物の具体的なキャリアや、客観的なデータをご紹介します。
ただし、STEAM教育は2008年頃にYakmanによって提唱され、日本では文部科学省が2018年頃から推進し始めた比較的新しい考え方です。よって、実際にSTEAM教育を受けたお子さんが、現在どんなお仕事をしているのかはデータが揃っていません。
STEAM教育に相当する教育プログラムの卒業生に関する事例をご紹介します
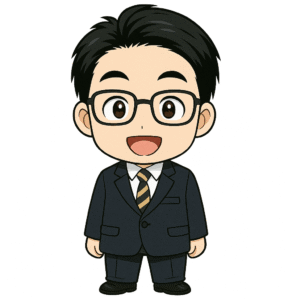
将来の姿 ①:好きを突き詰め、未来をつくる「研究者・技術者」
お子様の「なぜ?」という探究心は、専門分野で新しい発見や発明を生み出す力の源になります。
【事例1】宇宙探査機「はやぶさ2」開発者
Yさんは高校時代、国の特別な理数教育プログラム(スーパーサイエンスハイスクール)で高分子材料の研究に没頭しました。そこで身につけた「仮説を立て→実験し→検証する」という考え方のクセは、分野が異なる現在の宇宙工学の現場でも、すべての仕事の基本になっていると語っています。(出典:SSH卒業生活躍事例集)
【事例2】大学で「歯や骨」の謎を解く研究者
Hさんは、高校時代に「メダカの遺伝子研究」に没頭しました。これが生き物を好きになったきっかけのひとつです。高校時代の経験がなければ「科学者にも大学教員にもなっていなかった」と断言しており、高校時代の「好き!」という探究心が、そのまま将来のキャリアに直結した例です。(出典:SSH卒業生活躍事例集)
【客観的データ】ロボットコンテスト参加者の進路
アメリカの大規模な追跡調査によると、世界最大級のロボットコンテスト「FIRST」に参加した子どもたちは、そうでない子に比べて、大学で工学やコンピュータサイエンスを専攻する可能性が2倍以上高く、ITや工学の分野で働く割合も明らかに高いことがデータで証明されています。(出典:The First Longitudinal Study Final Report)
将来の姿 ②:分野を越えて、新しい価値を生み出す「起業家・ビジネスリーダー」
STEAM教育は、身につけた知識や技術を、社会の課題解決や新しいビジネスに繋げる力を育みます。
【事例3】データ解析の会社をアメリカで起業
Fさんは高校時代、部活動で使うソフトウェアが使いにくいことに気づき、分野を活かしてソフトウェアを自作しました。この「身近な課題を見つけ、技術で解決する」経験が、後にアメリカで会社を立ち上げる起業家精神の原点になったのです。(出典:SSH卒業生活躍事例集)
【事例4】世界的なコンサルティング会社で活躍
Kさんは、高校時代にルビーやサファイヤといった宝石の合成に挑戦。何度も失敗を繰り返す実験を通じて、自分で考える力は自然と訓練されたと語ります。この力は、コンサルティングという仕事で、新たな価値を生み出す際の土台となっています。(出典:SSH卒業生活躍事例集)
将来の姿 ③:文理の枠にとらわれない「社会の課題解決者」
STEAM教育で育つ力は、理系の仕事だけでなく、弁護士やジャーナリスト、社会活動など、文系の分野でも大きな武器になります。
【事例5】弁護士への道
SSH指定校の卒業生の中には、課題研究で高校生模擬裁判選手権に参加した経験がきっかけとなり、弁護士の道に進んだ事例が報告されています。複雑な事案から争点を抽出し、証拠に基づいて論理を組み立て、他者を説得するというプロセスは、法的な思考と探究学習のプロセスに高い親和性があります。
家庭でも育むことができるSTEAMマインドセット
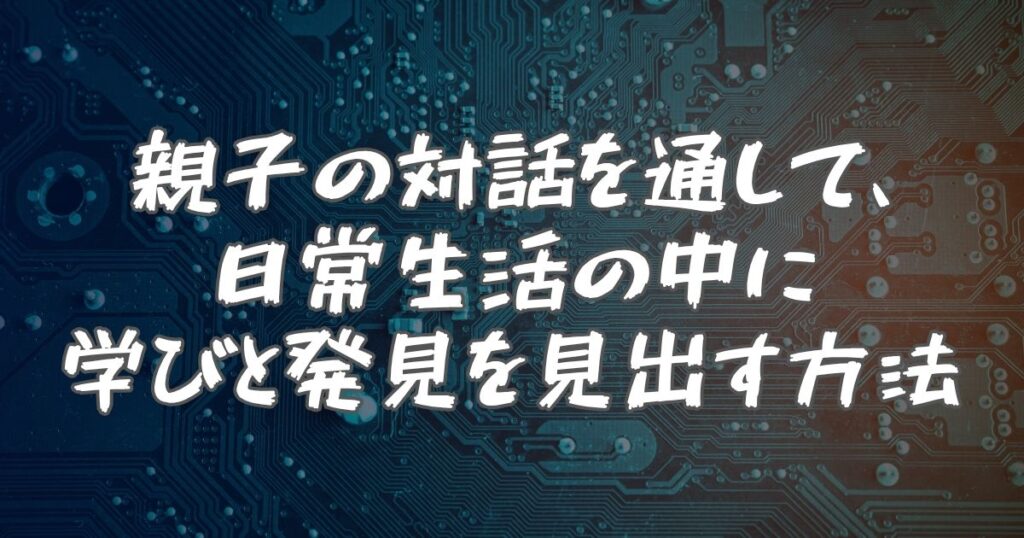
特別な教材や高価な機材がなくても、家庭はSTEAMの学びを育む最高の環境になり得ます。その鍵を握るのは「親子の対話」です。
好奇心の種を蒔く
お子さんが「これなあに?」「どうして?」と質問してきたら、それは絶好の学びのチャンスです。すぐに答えを教えるのではなく、「どうしてそう思うの?」「一緒に調べてみようか」と問い返すことで、子どもの探究心を深めることができま。逆に、保護者から「空はどうして青いのかな?」「このお料理は、どうして温めると色が変わるんだろうね?」といった問いを投げかけることも有効です。
プロセスを称賛する
子どもがブロックで何かを作ったり、絵を描いたりしているとき、完成した成果物だけを褒めるのではなく、その過程で見られた工夫や集中力、試行錯誤を具体的に言葉にして認めましょう。「この部分、何度もやり直して工夫していたね」「面白い色使いを考えついたね」といった声かけが、結果を恐れずに挑戦する姿勢を育みます。
日常生活を学びの場に変える
料理は、材料の計量(数学)、加熱による物質の変化(科学・化学)、盛り付け(芸術)が詰まった最高のSTEAM活動です。庭でのガーデニングは、植物の成長サイクル(科学・生物学)や土壌の管理(工学)を学ぶ機会になります。日常のあらゆる場面に学びのヒントは隠されています。
根拠に基づいて考える習慣をつける
お子様が何かを主張したとき、「どうしてそう思うの?」と根拠を尋ねる習慣をつけましょう。これにより、自分の考えを客観的なデータや事実に基づいて説明する、論理的・批判的思考の基礎が養われます。
まとめ
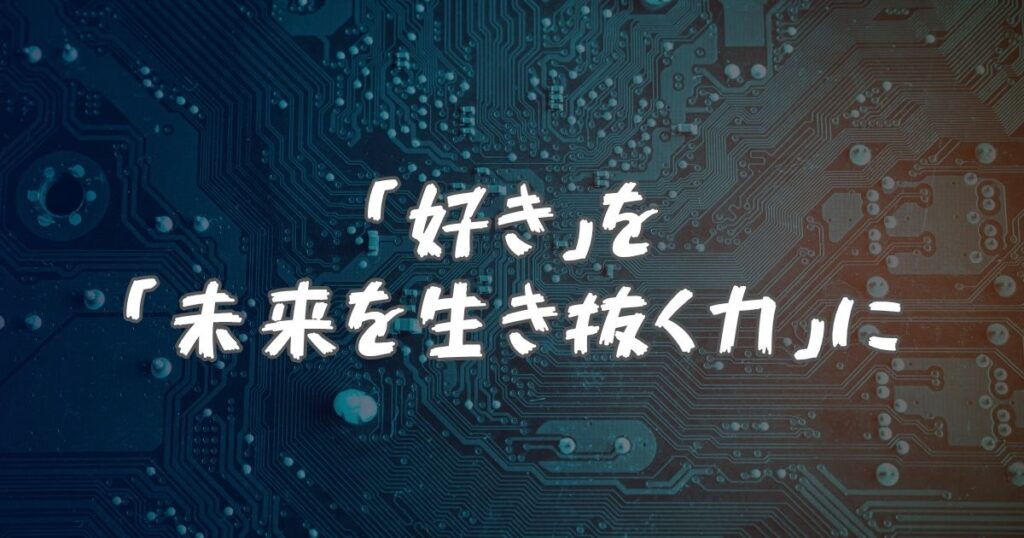
ここまで見てきたように、STEAM教育は、お子様を特定の職業に就かせるための訓練ではありません。
それは、予測できない未来を、「自ら課題を見つけ」「失敗を恐れずに試し」「多様な人々と協力する」という姿勢で、自分らしく力強く切り拓いていくための「一生モノの考え方のOS(基本ソフト)」をインストールするようなものです。
ご家庭での働きかけに加えて、お子様の「もっと知りたい!」という気持ちを、専門的な教室で伸ばしてあげることも素晴らしい選択です。
ブロック遊びやものづくりが好きなお子さんなら「ロボット教室」、ゲームが好きなら「プログラミング教室」、生き物や実験が好きなら「科学教室」が、最高の入り口になるかもしれません。
ほとんどの教室では、親子で参加できる無料体験会を実施しています。まずは気軽に参加して、お子様が夢中になれるものを見つけてみませんか?